子どもの頃は、時間を忘れて描くほど絵が大好きでした。けれど、その夢は一度手放すことに。
社会人となったある日、思いがけない出会いが再び濃密な制作の日々へと導いてくれました。
そして今、アートと静かな対話を通じて、人の心にそっと寄り添う活動をしています。
活動歴
2010年 鷲見綱一氏に師事。洋画を学ぶ
市美術展覧会初出品、初入選
2011年 市美術展覧会入選
2012年 全日本アートサロン絵画大賞展入選
個展開催
市美術展覧会入選
2013年 国立新美術館に入選作品展示
市美術展覧会入選
経歴や肩書きよりも、私が人生のなかで絵とどう向き合ってきたかを見ていただけたら嬉しいです。
よろしければ、その歩みの続きをこの下にあるインタビュー記事でご覧ください。
As a child, I loved drawing so much that I would lose all sense of time. But eventually, I had to let go of that dream.
Years later, while working, an unexpected encounter led me back into a deeply fulfilling period of painting.
Now, through art and quiet conversation, I hope to gently be alongside others and support their hearts.
Career Highlights
2010 — Studied Western-style painting under Kouichi Sumi; first submission and first acceptance into the City Exhibition
2011 — Accepted into the City Exhibition
2012 — Accepted into the All-Japan Art Salon Painting Grand Prize Exhibition; held a solo exhibition; accepted into the City Exhibition
2013 — Exhibited accepted work at the National Art Center, Tokyo; accepted into the City Exhibition
More than titles or credentials, I would be glad if you could see how art has been part of my life’s journey.
If you’d like to know more, please read the full interview.
第1部:「描けない時間を越えて」──自分を取り戻すように、また絵に出会った
1. 幼少期~学生時代:絵との最初の出会い「仮面の向こうに、本当の気持ちがあった」
子どもの頃から、図工の時間がいちばん好きでした。絵を描いたり、ものをつくったりするのがただ純粋に楽しくて、小学生のころは漫画のような絵ばかり描いていたんです。
中学に入って美術部に所属すると、デッサンなどにも触れるようになり、「もっと描きたい」と思うようになりました。特に好きだったのは、ポスターカラーのようなはっきりとした色合いで描く作品。高校進学後自由なテーマで描いた「仮面」の絵は、今でも心に残っています。カラフルに塗り分けられたその絵は、美術の先生にも「これは面白いね」と言ってもらえました。
なぜ仮面を描いたのか。今振り返ると、そこには思春期の私の感覚が表れていたのかもしれません。人の輪の中で、みんなが見せている顔が本心じゃないように感じていたんです。私自身も、小さい頃から大人に気を遣って育ち、自分のやりたいことを感情のままに伝えることが苦手でした。親の顔色を見て、怒らせないように過ごしていた。だからこそ、「仮面」を描くことで、自分の中の違和感や疑問を表現しようとしていたのかもしれません。
本当は、高校は美術科に進みたいと思っていました。でもすでに普通科への進学準備が進んでいて、親からも「今さら美術系なんて」と言われ、諦めざるを得ませんでした。母からは「美術なんて食べていけない」とも言われました。小学生のときに近所の絵画教室に通いたいとお願いしたこともありましたが、「絵なんて習うものじゃない」と一蹴されてしまって……。
私の夢は、もっと前から始まっていたんです。幼稚園の頃はデザイナーになりたくて、テレビに映るアイドルのひらひらした衣装を真似して描いていました。人形のドレスを着せ替え感覚で描くのがとても楽しくて。服そのものを縫うのは苦手でしたが、「色や形を考える」デザインの部分に惹かれていたのだと思います。
「人の意向に沿うのがベスト」——そう信じてきた私は、自分の気持ちに蓋をして、美術から離れる選択をしました。でも、あの時心の奥にあった「描きたい」という気持ちは、ずっと消えていなかったのだと思います。
2. 社会人と再びの絵:失恋がもたらした再始動「”描けるよ”その一言が道を開いた」
社会人になってからは、絵を描くことが日常からすっかり消えていました。美術館にはときどき足を運んでいたものの、自分で筆をとることはなくなっていたんです。
転機は30歳のとき。大きな失恋を経験し、日常にぽっかりと穴が空いたような感覚に襲われました。毎日、職場と家を往復するだけの生活。何かを変えたくて、友人に相談したとき、「絵、好きだったよね?」とある絵画教室を紹介してくれました。私が「描くことが好きだった」ことを、ずっと覚えていてくれたのが嬉しかった。
その教室は画材屋さんの2階にあり、社会人から小学生まで、さまざまな年齢の人が通っていました。

けれど、通いはじめて1ヶ月もしないうちに、私は少しずつ気が重くなっていきました。というのも、教室が画材店の中にあったため、毎回のように「この絵の具もいいよ」「これもどう?」と商品を勧められることが、だんだんとストレスになってしまったのです。
思い切って先生にその気持ちを打ち明けたとき、思いがけない言葉が返ってきました。
「僕のアトリエでも教室をやってるから、そっちに来てみない?」と。
そして「最初の絵を見たとき、“あ、この子は描けるな”って思ったよ」と力強く伝えてくれた先生の言葉は、心に深く残りましたね。
それが、「描く日常」が再び始まるきっかけです。
そのアトリエでは、美術科の高校に通う17歳くらいの男の子と、私と先生の3人だけという、ちょっと不思議な空間で、濃密な時間を過ごすことになります。4年ほど通い続けました。
先生の制作部屋が隣にあり、展覧会に出す作品の制作風景や、裏方の様子まで見せてもらえたのも貴重な体験でした。100号以上あるような大きなキャンバスの作品を間近で見たのは、その時が初めて。筆の運びや色の重ね方、作品が立ち上がっていくプロセス……「絵を描く」ということの奥深さを、あらためて肌で感じた時間でした。
3. 展覧会と大作への挑戦:自己回復の4年間「くすぶっていた想いが、大きなキャンバスで動き出す」
ずっと心の奥にくすぶっていた美術への想い。それをようやく形にしたい──そんな気持ちが、自分の中にあったことを、私は先生に正直に打ち明けました。親に反対され、遠ざけてきた道。でも、本当はずっと、諦めきれずにいたんです。
その話をしたあと、先生は私に公募展への出品を提案してくれました。
教室に通って2−3ヶ月後の2作目で、先生は、「目的があった方がいいから」と言い、次に描く作品のサイズを、なんと50号(縦横1メートル以上)に決めたのです。
こんな大きなキャンバスに絵を描くのはこの時が初めてでした。
たくさんの仮面を被った大人の中で、無表情で涙目の人形みたいな少女が中心に立っている。髪は白で、肌は青白く、半裸姿。生命エネルギーが感じられないこの少女は当時の自分を表現していたのかもしれません。この絵で初出品で入選しました。
残念ながら絵が残っていないのですが、大きなキャンバスに向かうようになって、学ぶことは本当に多くありました。
小さな絵なら、近くで描いていても全体が見えます。でも50号、100号の大作になると、細部を描いているうちに、全体のバランスがわからなくなる。「あれ?この色、浮いて見えるな」と気づいたときには、すでに他の部分との調和が崩れている──そんなことが何度もありました。
だから先生は、よくこう言っていました。
「描いては離れろ」
「構成をちゃんと考えてから描け」
感情のままに筆を動かすと、あとからの修正がとても大変です。余分に絵の具を使うことになり、時間も、労力も・・・。だからこそ、大作に必要なのは「計画性」。描く前に構図や配色を緻密に組み立てることが求められました。
大きな絵は、面積が広いぶん、たとえば余白にどう豊かな色を置くか、その“間”の工夫がとても難しい。私が描くと、どうしても単調になってしまうんです。
「つまらない」──と先生にもよく叱られました。
けれど、そのひとつひとつが、自分と向き合い、作品と対話する時間でもありました。描くことは、私自身を取り戻していく営みだったのだと思います。
4. ニューヨーク旅行で得た刺激と「変化」「本物を見て変わった、筆の感覚」
教室に通って描き続ける日々の中で、ふと、「本物の絵が見たい」と強く思うようになりました。ちょうどその頃、友人と一緒に3泊5日という弾丸スケジュールでニューヨークを訪れました。行けたのはたった2か所でしたが、それでも大きな収穫がありました。
海外の美術館では、作品にものすごく近づいて観ることができるうえ、写真撮影も自由。これは日本ではなかなか味わえない体験でした。特に油絵の場合、筆致や絵の具の重なり、質感などは、間近で見ないと絶対にわからない。その「生」の迫力に、圧倒されました。
帰国してすぐ、私は教室に行き、さっそく新しい絵を描き始めました。すると先生から「なんか変わったね」と言われたんです。具体的にどこがどうとは言われなかったけれど、「すごく良くなった」と。その言葉は、私の中でずっと残っています。
先生との会話はそんな具体的な言葉ではなく、感覚的な感じだったんです。
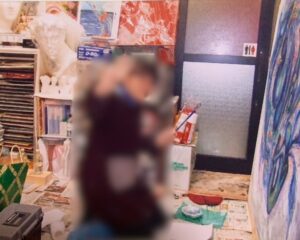
でも、いつも順調だったわけではありません。仕事帰りに描く絵は、先生に「堅いし、つまらない」と言われたこともあります。職場でのモードがそのまま絵に出てしまっていたのでしょう。それでも、「公募展」 というゴールがあったおかげで、気持ちの波があってもなんとか描き続けることができました。楽しかったですね。
絵を描くというのは、感情だけでは成り立たなくて、構成力や計画性、集中力が必要。でも、理屈だけでもだめで、そこに感情や衝動が乗ってこないと、心に響く絵にはならない。──そのバランスを取るのが、本当に難しいと感じていました。
シンプルな構図の絵ほど、描くのが難しい。線がほんの少しずれるだけで、全体の印象が崩れてしまう。そのわ ずかな違和感に気づけるかどうか、そこまでやり直すことが絵の完成度を左右します。
これはお金に変えられない体験ですね。

そして、作品づくりのたびに言われたのが、「もっと目を肥やしなさい」ということ。ぱっと見では単調に思えるような絵でも、よく見ると複雑な色の重なりや構造があると。
先生は今思えば、かなり厳しい人だったと思います。そして、先生の背中を見ながら、私は「作家として生きる」ということの厳しさと強さを肌で感じていました。感受性がものすごく強いからこそ、社会の枠組みに収まりにくい。でもその苦しみや葛藤さが、作品として表現されている。そんな先生の姿を間近で見られたことは、私にとってかけがえのない学びでしたが、そこまで「振り切る」ことはとてもできないと思いました。
第2部:「描くことで、生きなおす」──流産、依頼制作、スピリチュアルな感覚との出会い
1. 依頼されて描く──絵が誰かのためになる驚きと喜び「”描いてほしい” その言葉が描くことの意味を変えた」
そうして、約4年ほどアトリエに通ったあと、私は教室を卒業することになります。それまでにいくつかの公募展に出展し、国立美術館で展示されるという経験もさせてもらいました。3年目で入選したんです。それは、自分の中での大きな節目でもありました。
ちょうど34歳。女性としてこれからどう生きていくかを考える時期でもありました。絵にどっぷり浸かっていたら、女性としての人生をすり減らしてしまうのではないかという不安もあった。だから一度、現実の生活に戻ろうと決めたのです。
絵画教室をやめてしばらくして、また新たな道と出会うことになりました。
絵を離れていたある日、接骨院の先生との会話で「心理学に興味がある」と漏らしたことがありました。
そのとき先生が、「仕事に関係なくても、学ぶこと自体に意味がある」と背中を押してくれたんです。
そこからNLPという、心理とコミュニケーションについて学ぶ講座に2年ほど通いました。
振り返れば、あの学びがあったからこそ、今こうして“人のために描く”ことや、“対話を通じて気持ちを受け取る”という感覚につながっている気がします。
その後、結婚・出産と続き学びから遠ざかりましたが・・・ここで話していて私、色々やっているなと気がつきました(笑)40代にして、その全てが集約しそうな気がしています。
そんな中で、ふとしたきっかけから、あるオンライン講座に参加することになります。Zoomで開催される講座で、私は実家から参加していました。そのとき、実家の壁には、かつて絵画教室で描いた大きな絵が飾られていたんです。あの”少女と仮面”の絵です。
講座を担当していたのは、少しスピリチュアルな感性を持つ方で、量子力学なども交えたユニークな視点で話される先生でした。私は当時、仕事のことで悩んでいて、「何か変わるきっかけになれば」と参加していたんです。
Zoomの画面越しに私の絵を見た先生に、「それ、誰が描いたんですか?」と聞かれました。
そして、「今は描いてないんですよね?でも、絶対に描いた方がいい。私のために描いてほしい」
突然の言葉に、とても驚きました。ちょっと戸惑いながらも、「小さなサイズなら描けるかもしれません」と、その依頼を受けることにしました。これが今から6年くらい前のことです。
描くのが楽しかったですね。人にこんなに「描いてほしい」と言われたのが初めてのことだったからです。
「おまかせで描いてください」と言われ、その方のことを思い描きました。作品が完成し、郵送した数日後、その先生からメッセージが届きました。
「封筒を開けて、絵を取り出した瞬間に、涙が止まらなかったんです」と。

感受性の豊かな方だったので、何か深く感じ取ってくださったのだと思います。とにかく、「本当にお願いしてよかった」と、何度も言ってくださいました。
自分の絵でここまで喜んでくれるんだと感動しました。これが、誰かのために描くというきっかけにでしたね。
その絵は、海を描いたものでした。朝日か夕日かはもう定かではないけれど、太陽が海から昇ってくる──あるいは沈んでいく──そんな情景を描いた絵でした。どこか静かで、でも力強いエネルギーを感じるような作品でした。
2. 命を描くということ──依頼制作と喪失、感情と祈り「感情を整え、命を描く 絵が祈りに変わるとき」
その絵をFacebookに「人のために描かせてもらいました」って投稿したんです。そしたら、「自分にも描いてほしい」っていうコメントが入ってきて。
その次に描いた方のお仕事が、顕微受精の専門の方だったんですね。その方をイメージしていたら、「命の誕生」みたいなイメージが自然と浮かんできて。そういうテーマで描きました。「命が宿る瞬間」っていうタイトルだったかな。

絵は、たぶん1日か2日くらいで描きました。その方の写真を見て、スケッチブックにラフをバーッと描きながら手を動かしているうちに、イメージがどんどん湧いてきて。
サムホールという20cmくらいの小さなサイズです。大ききな作品を描いた経験があるからこそ、肩に力も入らず自然と手が動いていきました。
スピリチュアルな感覚があるかと聞かれると…あんまり大っぴらには言っていませんが、私の場合は、その方の写真を見ながら手を動かしているうちに、その人の内面に入っていくような感覚になるんです。
話をまったくしたことがない人のために描いたことはありません。オンライン上でも一度は会話したことがある方しか描いたことがないです。話すことで、その人の感性とか感覚みたいなものが、自分の中に残るんですよね。そして写真を見ると、それが引き金になって、自然とその人に入っていけるような感じになります。
私は、感情が整っていないと、人のために絵を描くことができないと思っています。やっぱり、エネルギーって絵に入ると思うんですよね。だから、負の感情を抱えたまま描いたものを誰かに渡すのは、ちょっと違うなと思っていて。
そうして描き続けるうちに神社に行くことが増えました。「上とつながる」みたいな感覚があるんですよね。仕事を少し離れていた期間に、そういう感覚がどんどん研ぎ澄まされていった気がします。
そこから自然と、龍の絵を描くようになりました。見えるわけではありません。でも、龍神様のような存在を「感じる」ことがあるんです。「気のせい」と言われたらそれまでだけど、私にはそう感じられる。だから、それを絵にするようになりました。
宗教に傾倒しているつもりはありません。でも、以前よりずっと、「見えないものの存在」を信じるようになりました。絵を描くことは、いつの間にか、祈ることに近づいてきたのかもしれません。
3. 転機となった流産の絵と、人生を変えた痛み「いちばん苦しい経験が、いちばん大きな絵になった」

少し時間を巻き戻すのですが、最初の依頼の絵を描いてからしばらくして、流産を経験します。すごく悲しいし、体もしんどいけれど、その時のことを形に残さないといけないと思ったんです。
それがこの絵です。私の人生の一部だと思ったから、インスタのアイコンにしています。
これは、流産手術のため手術台の上にいた自分の記憶と感覚です。
麻酔で意識は飛んでいるはずなのに、赤色のトンネルの中で、回転しながら浮遊していました。すーっと体が降りていって、「地面に体がつくなー」と思ったら、急に声が聞こえました。
「先生、麻酔が切れます」
先生が「もうちょっとだ」と。
きっと身体の中の胎児やその付随物を吸っていたと思います。音が聞こえていたので。そしたら、体がストンと落ちて、意識が戻った。終わりましたと言われました。
私は、その時子供と一緒に、産道にいたのではないのか?子供の魂を感じ取ったのかもしれないと思いました。
これまでの私の人生で一番辛かった出来事です。今でも思い出すと辛いけれど、意味があったからこそ、ここでそのことを話していて、誰かの役に立ちたいと思っているんです。
あの経験がなければ、「趣味で絵を描く」で終わっていたと思います。
4. 和紙との出会いと日本的表現への関心「和紙が導く、日本らしい絵の深みへ」
そして、和紙を使った作品も、新たな私の表現として加わりました。
使い始めたのは、富士山の絵を描いていたときでした。雲を描こうと思っていて、そのとき、たまたま手元に和紙があったんです。
以前から、美濃和紙にすごく惹かれていて。よく買いに出かけていたんです。理由は自分でもはっきりとはわからないけど、なんとなく「いいな」と思っていて。それで、いつ使うかわからないまま和紙を買って帰っていたんですね。家にいくつかストックがありました。
和紙を主役にするわけじゃなくて、絵のスパイスとして、部分的にちょこちょこっと使ったのが最初でした。貼って、そこに色をのせたり、質感を活かしたり。そんな感じで自然と使い始めました。
やっぱり日本的な絵──たとえば富士山とか、龍とか、そういうモチーフには和紙が合うんですよね。自分でも描いていて、しっくりくるというか、絵に深みが出るような感じがします。
今描いている作品も、和紙を使っています。ある自治体で、和紙の普及のためにやっているアートと和紙のコラボのような公募展があって、そこに出すための作品です。応募条件として「和紙を使うこと」という規定があったので、今は和紙がメインになっています。
ただ、「どうしても使いたい!」っていう強い気持ちがあるわけではなくて、「面白いから使ってみようかな」っていう感覚です。素材としての面白さや、手触り、透け感、そういうものを楽しみながら描いている感じですね
第3部:「これから描く、私のかたち」──絵と対話、仕事と命、すべてがつながる場所へ
1. 仕事と生き方の再構築:20年の仕事と違和感「このままじゃ後悔する 生き方を見つめ直す」
今、20年近く続けてきた仕事があるんですけど、それが最近すごくエネルギーを消耗していて。「これは自分の生き方じゃないな」と感じることが増えてきました。
これまで私は、自己投資してきましたが、職業がらアウトプットする機会はなかなかなかったけれど、溜めてきたものを誰かの役に立てたい、って思うようになってきました。
人生の後半として、そういう生き方があってもいいのかなって。いや、そう生きたいって思うようになったんです。
「死ぬ時に後悔することって、“もっとお金を稼げばよかった”じゃない。いちばん多いのは、“もっと冒険すればよかった”なんです」
それを聞いたときに、「ああ、私、このままやりたいことをやらずに明日死んだら、絶対に後悔する」って思ったんです。経済的な心配はもちろんあるけど、それでも、やらなかったことを後悔するほうが怖い。それだけは確信していて。
だから、自分の持っている資質で、世の中のために何か貢献できるような生き方をしたいなって。そう強く思うようになりました。
2. アート×心理サポート:2本柱のビジョン「人に寄り添う、絵と対話のかたち」
たとえば──迷っている人とか、自分が何をしたいのか分からなくなっている人の背中を、少しでも押せたらいいなって思うようになりました。
そういう方に対して、カウンセリングのようなことをさせてもらいつつ、もしその方がアートに興味があれば、その方をイメージして絵を描かせてもらう。そんなサービスができたらいいなというビジョンがあります。
実はこれまでに、体調を崩して、2回ほど仕事を離脱したことがあります。本当に、長いトンネルを歩いているような、つらい日々でした。
「なんでこんなに一生懸命働いてるのに、神様は私にばっかり罰を与えるんだろう」って、思ってしまうこともありました。理不尽さとか、報われなさとか、そういう思いが何度も心の中に浮かんできて。
でも、今振り返ると──その経験があったからこそ、人の痛みが分かるようになった気がします。だからこそ、その経験を無駄にせず、誰かの役に立てることに使いたいって思うようになったんです。
体調を崩すって、単に「身体がしんどい」というだけじゃなくて、心のバランスも崩れるし、自分の存在そのものが揺らぐような感覚があって。そういう経験をした人にしかわからないことって、きっとたくさんあると思うんですよね。
だから、同じように苦しんでいる人がいたら、「私はこういうふうに乗り越えてきたよ」って、寄り添える存在になりたい。無理に励ましたり、元気づけたりするんじゃなくて、その人のペースで、その人の痛みに静かに寄り添うような存在でありたいって、今は思っています。
そして、日本の文化を発信したいという気持ちも、少しずつ強くなってきました。日本人に売るというよりも、海外の人に向けて──「龍」という存在も含めた日本の精神性を、アートを通して伝えていけたら、と。

だから、私の中には今、「アートで海外へ」「カウンセリングでは日本の人たちへ」という、2つの軸があるんです。まだ実際に動き出しているわけではないけれど、頭の中にははっきりとしたビジョンがあります。
3 言葉と気づき:対話の力「その人の言葉から、心の景色が見えてくる」
私にとって、絵は手段のひとつであって、中心にあるのはやっぱり「人」なんですよね。
たとえば、絵は絵として置いておいて、こうやって話をしていく中で──これはたぶんNLPの知識があるからだと思うんですけど──私は「質問の力」ってすごく大事だと思っていて。
どう相手に問いかけるか。その問いに対して返ってくる言葉には、その人の心理状態がすべて表れていると思うんです。
「気持ちは見えない」とよく言われるけれど、私は、言葉こそがそのまま気持ちなんじゃないかと思っていて。みんな同じ言葉を使うわけじゃないし、その人ならではの言葉選び、その人のフィルターを通って出てくる表現に、心の状態が現れていると思うんです。
もちろん、学問的な観点もあるけれど、それに加えて、私はちょっと第六感的というか、スピリチュアル寄りな感覚で、人とつながってしまいやすいところがあって。人っていう存在が、他の人よりも見えやすいのかもしれません。
だからこそ、アートにも表現しやすいんです。私の場合はたまたま、それが「絵」という手段だったというだけで、もしその人がアートに興味がなければ、言葉だけで終わることもあるかもしれません。
絵にこだわっているわけではなくて、根本には「人」があって、その人の言葉や気持ちに寄り添うこと。それが、私のテーマなんだと思います。
そしてたぶん、これからもずっとそれを描いていくのだと思います。
